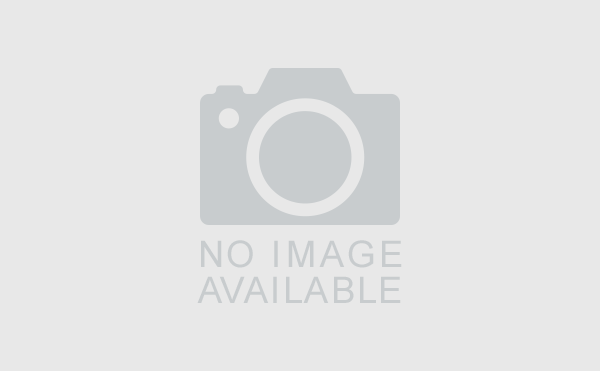読売新聞に市民科学の記事「生物多様性の研究 市民が力」が掲載されました
11月4日の読売新聞夕刊に「生物多様性の研究 市民が力」が掲載されました。
記事では、主に京都大発のベンチャー企業「バイオーム」が開発したスマートフォン向け無料アプリ「Biome(バイオーム)」の紹介と、市民科学を利用したヤマカガシの研究について、紹介されています。
「Biome(バイオーム)」では、利用者が撮影した動植物の写真をAIが位置情報や季節を踏まえて種の候補を表示し、図鑑としてコレクションできること。また、マップ機能で他の利用者が投稿した動植物の情報を共有できる事を紹介しています。
また、市民科学が有効な例として、北海道大や京都大などのグループがヘビの一種「ヤマカガシ」の色や模様について、市民に呼びかけて全国的に調べた結果を発表しました。方法として、「ツイッター(現X)」にて市民に写真提供を依頼、 爬虫類ファンの反響が大きく、青森県から屋久島(鹿児島県)まで1000枚近くが集まり、先行研究では六つの型に分けられていたが、集まった写真で少なくとも約120種類の色と模様の組み合わせを確認。「関東型」「九州型」など地域名を持つ種類が、実際はより広範囲に散っている事が分かりました。
記事の全文は2025年11月4日の読売新聞夕刊または、以下の読売新聞電子版(Webサイト・アプリ)にて閲覧する事ができます。
【物の「新種」あなたも見つけられるかも?市民が撮影した写真で生物多様性の研究進む…アプリ「バイオーム」も後押し】
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20251104-OYO1T50053/
小堀代表は、取材の中で専門家としての意見を求められ、